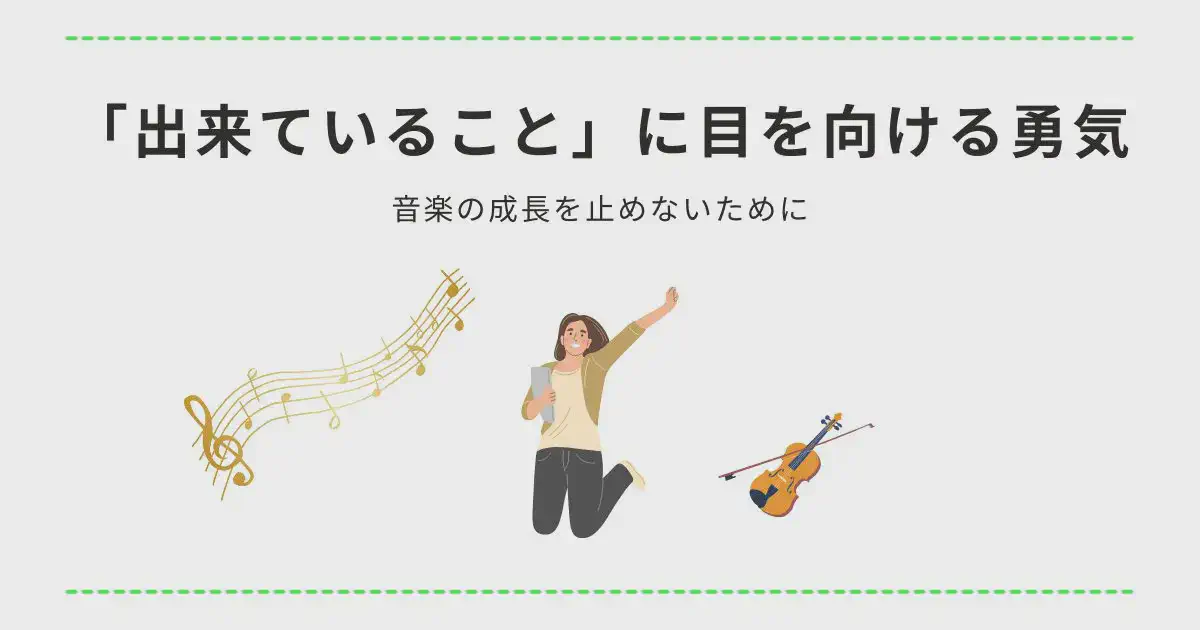レッスンで刺さった一言
「出来ていないことにフォーカスしても上手くいかないときは、今出来ていることをやって観察してみてください。」
レッスンの終盤、先生が何気なく口にしたその言葉が、不思議なほど心に残った。その日は、思うように音が出せず、練習しても練習しても形にならず、内心焦りでいっぱいだった。そんな自分の姿を見透かしたかのように、先生は穏やかに続けた。
「“なんで出来ないんだろう?”と同じくらい、“なんで出来るんだろう?”を考えてみてください。」
その瞬間、私はハッとした。出来ていないことばかりに目を向けて、出来ていることを見ようとしていなかった――そんな自分に気づいたのだ。
出来ないことへの執着
音楽を続けていると、「出来ないことのリスト」は尽きることがない。音程、弓の角度、フレーズの流れ、表現の方向性、音の立ち上がり。それらを一つひとつ修正しようとするうちに、気づけば頭の中は「改善点」でいっぱいになる。
レッスンでの注意を真剣に受け止めるほど、自分へのダメ出しが増えていく。「ここが違う」「まだ足りない」「もっと練習しなきゃ」。その思考は一見向上心のようでいて、実は自分を追い詰める方向に働くこともある。
出来ない自分を否定し続けていると、音も、心も、どこかぎこちなくなる。弓が硬くなり、音が荒れ、表現の幅が狭まる。本来音楽が持っている“自由さ”や“呼吸”が、窮屈な意識の中で失われていくのだ。
「出来ていること」に光を当てる
そんなときこそ、先生のあの言葉を思い出す。
「出来ていないことばかり見つめても、上手くいかないときがあります。 出来ていることを観察してみてください。」
考えてみれば、うまくいった瞬間を分析することはあまりなかった。上手く弾けたときほど「まあいいか」で流してしまう。でも、“出来ている”というのは偶然ではない。その裏には必ず、身体の使い方や意識の置き方といった“再現可能な条件”が隠れている。
出来ていることに目を向けるとは、「何をすれば音が良くなるのか」「どうすれば自然なフレーズになるのか」を、自分自身から学ぶことでもある。それはつまり、自分の中にいる“もう一人の先生”に耳を傾けることだ。
ある日の練習での気づき
スピッカートの練習をしていたある日。音が跳ねすぎてしまい、どうしても安定しなかった。焦って弓の速度や角度をいじっても改善せず、ついには肩に力が入り、音はますます乱れた。
そんなとき、ふと以前スムーズに弾けた日のことを思い出した。「あの日はなぜ出来ていたんだろう?」そう考え、当時の動画を見返してみた。
映像の中の自分は、表情が柔らかく、呼吸が自然だった。弓の速度も一定で、音が“跳ねる”というより“浮かぶ”ように響いていた。つまり、弓を「動かそう」とする意識が強すぎると音が硬くなり、一方で「音を聴こう」としているときは、自然に跳ねていたのだ。
「出来ていたときの自分」を観察することで、問題の原因が見えてくる。そしてそれを意識的に再現することで、安定したスピッカートを取り戻せた。この経験は、私にとって“観察の力”の大きさを実感する瞬間だった。
年齢とともに変わる「努力の質」
学生の頃は、時間をかけて練習すればするほど上達を感じられた。けれど、年齢を重ねるにつれて、同じ方法では伸びにくくなっていく。体力の変化、集中力の持続、精神的な波――それらが上達のペースに影響を与えるようになる。
「もっと練習しなければ」と思っても、時間には限りがある。そして、ただ“量”をこなすだけでは、壁を越えられなくなる。そんなときこそ必要なのは、「努力」よりも「観察」だ。
自分の身体の使い方、音への反応、心の状態。それらを丁寧に見つめることが、今の自分に合った成長の道を開く。言い換えれば、“出来ている自分”を理解する力こそ、成熟した努力の形なのだ。
「出来ていること」を見つけるための3つのステップ
- 成功の瞬間を記録する
- レッスン中や練習中に「今の音、良かった」と感じたら、その理由を即座にメモする。
- 弓のスピード、左手の感触、息の流れ――どんな小さなことでもいい。
- “感覚の記録”を残すことで、後から再現しやすくなる。
- 感覚を言葉にする
- 「力が抜けていた」「呼吸が深かった」「音が伸びた気がする」など、
- 曖昧な感覚もできるだけ具体的に言語化してみる。
- 言葉にすることで、無意識の動きを意識下に置けるようになる。
- うまくいかない時と比較する
- 「出来た時」と「出来なかった時」を比較すると、違いが鮮明になる。
- “失敗の原因”を探すより、“成功の条件”を見つけることを目的にする。
- それが、練習を建設的に変える第一歩になる。
出来ていることを認める勇気
「まだまだです」「全然出来ていません」音楽を学ぶ人ほど、謙虚な言葉を口にしがちだ。けれど、出来ていることを認めるのは決して驕りではない。それは、自分の中の成長を“肯定する力”だ。
自分の中にある良い部分を観察し、理解し、信じる。その行為は、音楽を続ける上での大きな支えになる。なぜなら、成長は「欠点の修正」ではなく、「良いものを育てること」だからだ。
「観察」は最も静かな練習
観察とは、ただ“よく見ること”ではない。それは、自分を丁寧に扱うことでもある。
焦りや比較の中では見落としてしまう小さな変化に、静かに気づくための心の余裕を持つこと。それが「観察する力」の本質だ。
出来ないことにフォーカスしていると、いつの間にか心が固まる。出来ていることを観察すると、逆に心がほぐれ、音も柔らかくなる。人間の意識と音の関係は、驚くほど密接なのだ。
「観察力」は音楽以外にも通じる
この考え方は、音楽だけに限らない。人間関係でも、勉強でも、仕事でも同じだ。「出来ないところ」ばかり見つめると、自己否定が強くなる。でも、「出来ている部分」を認めて観察すれば、自然と改善点も見えてくる。
自分の中の“良い流れ”を知ること。それは、どんな分野においても再現性のある成果を生み出す鍵になる。
レッスンの帰り道で思ったこと
先生の言葉を聞いた日の帰り道、ふと歩きながら思った。私はずっと、「出来ない自分をどうにかしなきゃ」と焦っていた。でも本当は、「出来ている自分」をもっと見てあげる必要があったのかもしれない。
それからしばらく、練習ノートの書き方を変えた。「反省点」の欄の隣に、「今日出来たこと」を書く欄を作った。たとえば、「音の響きが前より広がった」「集中して通せた」「一度も立ち止まらず弾けた」など、小さなことでも書き留めていく。
そうして数週間が経つと、不思議なことに“出来ないこと”の方にも自然と光が当たり始めた。否定ではなく観察によって、課題が少しずつ整理され、練習が前向きで穏やかな時間に変わっていったのだ。
成長とは、「出来ている理由」を増やすこと
上達の道は、常に“出来ないことを減らす”方向に意識が向きがちだ。けれど本当の成長とは、“出来ている理由”を増やしていくことなのかもしれない。
今日の自分が、昨日より少しでも自然に音を出せたなら、それは確かに一歩前進している証拠。その小さな前進を丁寧に観察していくことが、長い音楽人生を支える大切な力になる。
おわりに
練習を積み重ねるほど、私たちは“出来ない理由”を探す名人になってしまいます。けれど、成長の種はその逆側――“出来ている理由”の中にこそ潜んでいます。焦りを手放し、今日出来た一つの音を丁寧に観察してみてください。それは、あなたの音楽を未来へ導く静かな力になるはずです。