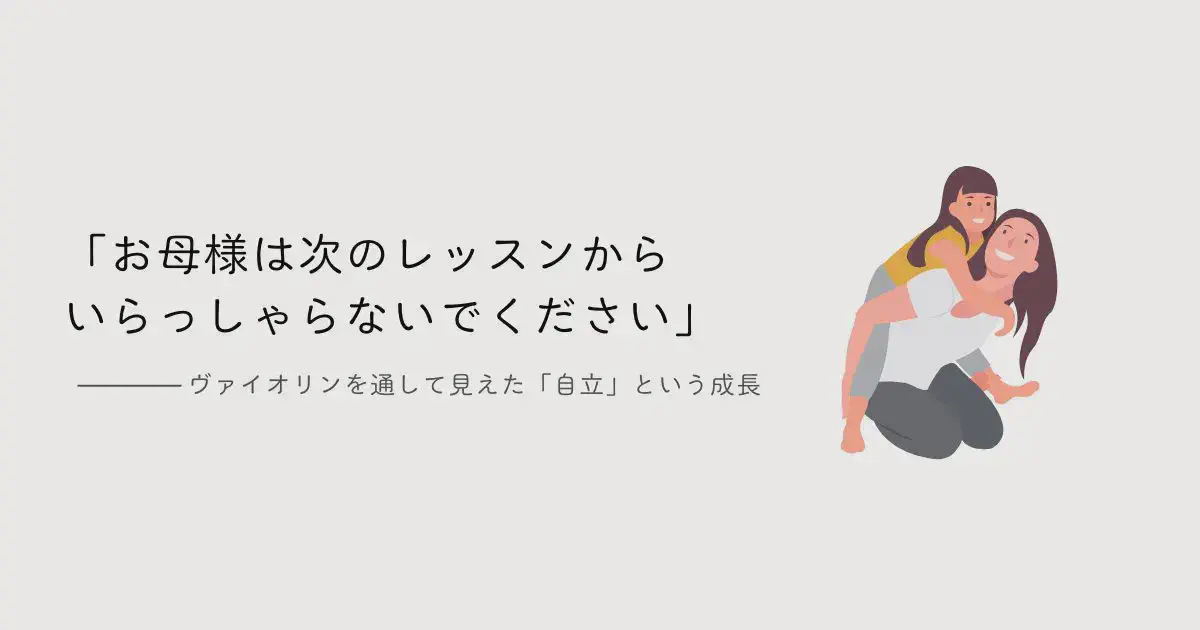はじめに ― 言葉の奥にある「信頼」
「お母様は、次のレッスンからいらっしゃらないでください。」
その言葉を初めて聞いたとき、私は中学2年生でした。ヴァイオリンの先生の穏やかな声が、なぜか心の奥に深く響いたのを今でも覚えています。突然の宣告に、隣で聴いていた母は少し驚いた様子でした。けれど、私の心の中では――「やっと、ひとりの音楽家として見てもらえた」という静かな喜びが広がっていたのです。
それまでの私は、母と一緒にレッスンへ通うのが当たり前でした。小学生のころからずっと、母が隣の椅子で私の音を聴き、先生の言葉をノートに書き留めてくれていたのです。だから「ひとりで大丈夫なのか」という母の不安は当然でした。でも、あの瞬間、私は初めて“自分だけの音楽”と向き合う時間を与えられたのです。
レッスン室にあった「見えない支え」
思えば、母がそばにいてくれたレッスンの日々は、とても安心感に満ちていました。楽譜を忘れたときも、弦が切れてしまったときも、母がすぐに助けてくれた。レッスン後には「今日は上手にできてたね」と微笑んでくれることもあれば、「先生が言ってたここ、もう一度確認しよう」と一緒に考えてくれることもありました。
けれどその安心感の裏側には、ほんの少しの“甘え”も潜んでいました。先生の言葉をすべて理解できなくても、「あとでお母さんがメモを見て教えてくれる」と思ってしまう。うまくいかないときも、「お母さんが何とかしてくれる」と心のどこかで思っていたのです。
そんな中で告げられた先生の一言。それは決して冷たさではなく、「そろそろ自分で考え、決め、動く時期だよ」という、温かな信頼のメッセージでした。
初めての「ひとりレッスン」― 音の中に取り残されて
母がいないレッスン初日。扉が閉まった瞬間、教室の空気がいつもより重たく感じました。先生の前に立つ私の手は、少し震えていたと思います。
「じゃあ、スケールからいこうか。」
その一言に、私は大きく息を吸って弓を置きました。その音が、思っていた以上に空間に響き渡る。母がいないだけで、音がこんなに“自分のもの”として返ってくるのか――。不思議な感覚でした。
先生の指摘は相変わらず多く、しかも細かい。弓の角度、左手の形、音程のわずかなズレ、フレーズの方向性……。まるで音の世界の細胞まで見透かされるような濃密さ。一瞬たりとも気が抜けません。
それでも、その時間はなぜか“自由”でした。母の視線を気にすることもなく、自分の音と先生の言葉だけに、全神経を注ぐことができる。レッスンの密度は、今までの何倍にも感じられたのです。
「見られる自分」から「聴く自分」へ
母がそばにいるとき、私はいつも“見られている”意識がありました。もちろんそれは、母の愛情からくる見守りであり、私を信じるまなざしでした。けれど、思春期の私にとってその視線は、少しだけ窮屈にも感じていたのです。
1人でレッスンを受けるようになってから、私は「見られる自分」から「聴く自分」へと変わっていきました。先生の言葉をノートに書くのも自分。注意されたことをどう直すか考えるのも自分。その過程で、自然と「音を聴く耳」も研ぎ澄まされていきました。
以前は、母が書いたメモを見ながら練習していたのが、今では自分の言葉でノートを作るようになりました。「音程が不安定」ではなく、「ポジション移動のときに左手が浮いている」など、自分で具体的に原因を探し、言葉にする習慣が生まれたのです。
それはまるで、音楽の世界に“自分専用の言語”を作り始めたような感覚でした。
親の「距離」は、子どもの「自立」を育てる
母は最初、先生の提案に少し戸惑っていました。「先生の言葉はとても専門的だし、あなたひとりで理解できるかしら?」でも、私が「大丈夫、やってみたい」と言うと、静かに笑って「じゃあ、任せるわ」と言ってくれました。
その“任せる”という一言が、どれほど大きな意味を持っていたか、今ならわかります。親が子の成長を信じて「一歩引く」こと。それは、愛情を手放すことではなく、信頼を「行動」で示すことなのだと感じます。
母がレッスン室の外にいることで、私は初めて「自分の責任で弾く」という意識を持ちました。うまく弾けなかったとき、「お母さんのせい」でも「先生のせい」でもなく、“自分自身の音”として受け止める。それが本当の意味での「音楽との対話」の始まりだったのです。
「自立」には“孤独”がつきもの
ひとりでレッスンを受けるようになってからしばらくは、帰り道が少し寂しく感じられました。いつもなら母と「今日はどうだった?」と話しながら歩いていたのに、その時間が静寂に変わる。
けれど、その“静けさ”が、だんだんと心地よくなっていきました。レッスンで得たことを頭の中で整理し、自分の音を思い返す――その静かな時間が、学びの一部になっていたのです。
「孤独」というとネガティブに聞こえるかもしれませんが、音楽家にとっての孤独は「聴く力」を育てる時間でもあります。自分の中に響く音を見つめる。他者の意見ではなく、自分の感覚を信じる。その積み重ねが、やがて“表現者”としての自立につながるのだと思います。
レッスンの質が変わる瞬間
母が同席しなくなってから、レッスンの進み方にも変化が生まれました。先生との会話が、より「対話的」になったのです。
以前は先生が説明し、母がそれを記録する――という“伝達型”のレッスンでした。しかし、1人になると、私がその場で質問し、自分の理解をその都度確かめるようになりました。
「今の弓のスピードで、どんな響きが理想ですか?」「このフレーズのクレッシェンド、どこから意識すれば自然になりますか?」
そう尋ねるたびに、先生は少し驚いたように笑って答えてくださいました。“教えられる”側から“学びに行く”側へ。レッスンが一方通行ではなく、双方向の時間に変わったのです。
その頃から、音楽の面白さが格段に増しました。自分の意見を持ち、音に対する問いを立てる。その思考こそが、成長を一気に加速させていったのです。
母のまなざし ― 離れても、そばにいる
母はその後も変わらず私を支えてくれました。レッスンには来なくなっても、家での練習を優しく見守り、発表会の日には一番前の席で拍手を送ってくれる。
「あなたが自分で考えて弾いている姿を見るのが、何より嬉しいの。」
その言葉に、私は胸がいっぱいになりました。母にとって“手を離す”ということは、決して簡単なことではなかったはずです。でも、私の成長を信じて見守る――その強さがあったからこそ、私は音楽の道で一歩を踏み出せたのだと思います。
教える側になって気づいたこと
今、私自身が教える立場になってみると、あのとき先生がなぜあの一言を言ってくださったのかが、ようやくわかります。
子どもが音楽と向き合ううえで、“親の関与”はとても大切です。けれど、ある時期を過ぎると、その支えを「距離」に変えていくことが、より大切になる。
レッスンで生徒がひとりで立つ時間は、単に「親を外す」ことではなく、「生徒自身の耳と心を信じる」ための訓練なのです。
だから私は、教えるときも同じように思います。「手を出す」より、「見守る」ことのほうが勇気がいる。でも、その勇気を持てた瞬間、子どもたちは自分の力で驚くほど成長していきます。
おわりに ― 「ひとりで立つ」ことの美しさ
あの日、先生に言われた一言――「お母様は、次のレッスンからいらっしゃらないでください。」
それは私にとって、“音楽家としての第一歩”を告げる合図でした。母のそばを離れて初めて、私は「自分の音」を聴くことができた。それは少し寂しくて、でもどこまでも自由な瞬間でした。
今でもステージに立つたびに思い出します。誰かに見守られていた時間があったからこそ、今こうして、ひとりで音楽を奏でることができるのだと。
自立とは、孤独に耐えることではなく、“信じてもらう経験”の積み重ね。そして、それに応えようとする“誇り”のこと。
音楽が教えてくれたのは、「ひとりで立つことの怖さ」よりも、「ひとりで奏でることの美しさ」でした。
レッスンにおける「親の距離感」は、子どもの成長を左右する大切な要素です。見守る勇気、手を離す勇気――その両方が、音楽の中での“自立”を育てます。ヴァイオリンという楽器を通して、子どもが自分自身と向き合う瞬間を大切に。それが、音楽と生きる力を育む第一歩です。