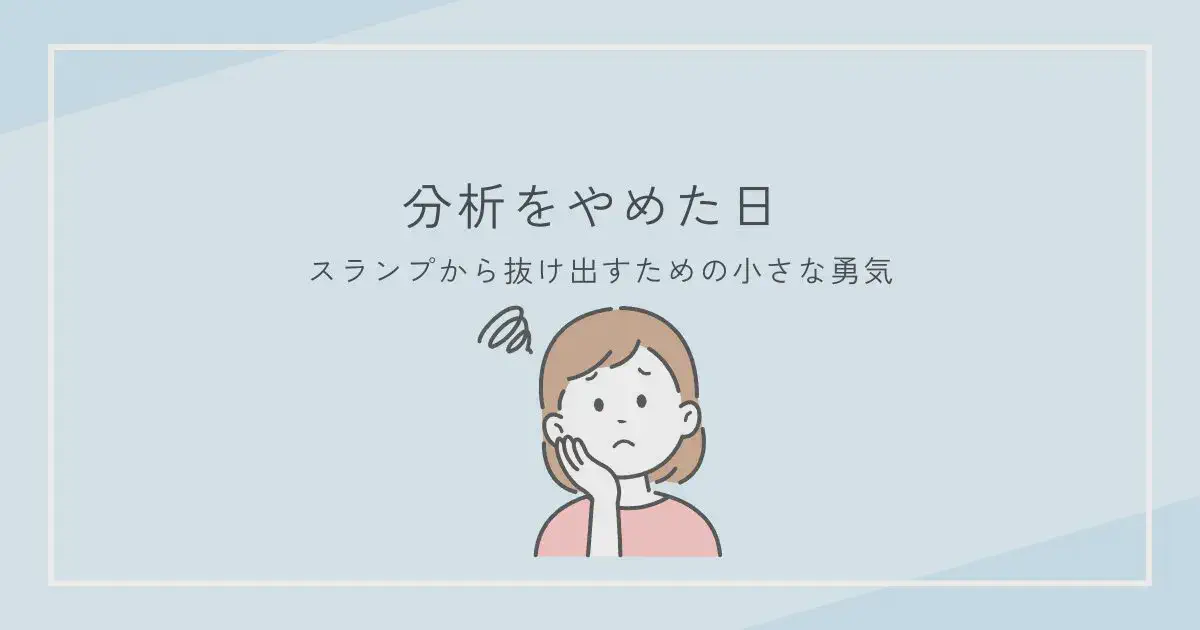絶賛スランプ期、到来
演奏家として生きていると、誰にでも「うまくいかない時期」は訪れます。それは、努力を怠っているからでも、情熱を失ったからでもありません。むしろ、真剣に音楽に向き合っている人ほど、その壁は突然やってきます。
私にも、そんな「絶賛スランプ期」と呼べる時期がありました。どれだけ練習を重ねても、音が思うように鳴らない。舞台に立っても、心が解き放たれない。終演後の拍手の中で、どこかに置き忘れてきた自分を探しているような感覚。
それでも私は、諦めることだけはできませんでした。原因を突き止めて、改善して、前に進みたい。そんな一心で、私はノートを開き、毎回の本番ごとに「反省と分析」を書き続けていました。
分析ノートの山 ― 「努力の証」がいつしか「重荷」に
演奏後の反省ノートには、びっしりと書き込みが並びました。
- 音の立ち上がりが甘い
- フレーズの方向性が不明確
- 表情づけが均一すぎる
- 弓の返しが雑になる
- 緊張で右手の圧が強くなる
気づいたことを一つ残らず書き出し、それを分析して、原因を考える。そして次の本番では、改善策を立てて臨む――。
最初のうちは、この方法で確かに成長を感じていました。自分の弱点を言語化できることは、音楽家としての大きな強みです。「感覚」だけに頼らず、冷静に自分を見つめ直すことで、技術面の精度は上がっていきました。
けれど、ある日ふと気づいたのです。ノートのページが増えるごとに、私の演奏はどこか“息苦しく”なっていったのです。
「次こそは」―終わりのない分析スパイラル
演奏を終えるたびにノートを開き、できなかった部分を洗い出す。「このミスを次はなくそう」「次の舞台ではもっと良くしよう」。そう思って努力を重ねるのは悪いことではありません。
でも、その分析がいつしか「呪縛」になっていく瞬間があります。
ステージ上で音を出すたびに、心の中で誰かが囁くのです。「ここ、また弱点の部分だよ」「今の、前回と同じミスだね」と。
その声が大きくなるほど、音楽は「自由」から遠ざかっていきました。自分を律するために始めた分析が、いつしか自分を縛る鎖になっていたのです。
本来、音楽とは“瞬間の芸術”です。再現性を求めすぎれば、その瞬間の「生きた音」が失われてしまう。頭ではわかっているのに、どうしても抜け出せない。そんなもどかしさの中で、私はどんどん音を出すのが怖くなっていきました。
「その分析、やめてみたら?」―先輩の一言
ある日、尊敬する先輩に思い切って相談しました。「本番で思うように弾けなくて、でも毎回分析して、改善しているのに結果が出ないんです」
先輩は私のノートをしばらく眺めたあと、静かに言いました。
「……その分析、やめてみたら?」
その瞬間、私の中で何かがスッとほどけたのを感じました。
「え?」と驚く私に、先輩は続けました。
「あなたはもう十分、自分を見つめてる。 これ以上“直そう”としなくていい。 一度、“音楽を感じる”だけの時間を過ごしてごらん。」
まるで、今まで握りしめていた鉛筆をやっと手放したような感覚。それは叱責でも励ましでもなく、まっすぐな「赦し」の言葉でした。
「直す」より「感じる」―バランスの再発見
分析をやめてみる、というのは思った以上に怖いことです。努力を止めてしまうような気がして、不安になる。でも、私は先輩の言葉を信じて、あえてノートを閉じてみました。
次の本番。ステージに立つ前、ノートもペンも持たず、ただ深呼吸をしました。「今日は、自分の音をただ味わおう。」
そのとき、久しぶりに“音を出す喜び”が戻ってきたのです。ひとつひとつの音が、空気の中でゆっくりと広がっていく。頭の中に「間違えるかも」「直さなきゃ」という声がない。かわりにあるのは、純粋な「音への愛しさ」だけ。
不思議なことに、結果も自然とついてきました。演奏後、客席から「今日は音が生きていましたね」と言われたとき、私は涙が出そうになりました。
「努力」は正しい。でも、いつも「必要」ではない。
分析や努力は、音楽家にとって大切な武器です。けれど、その武器をずっと握りしめたままでは、手が疲れてしまう。ときには、武器を置いて休む勇気も必要なのです。
完璧を目指すあまり、私たちは「間違いを恐れる自分」を作ってしまいがちです。しかし、音楽は「間違えない人」が美しくするのではなく、「感じる人」が美しくするもの。
それに気づいた瞬間、私は自分の中で“努力の定義”が変わりました。努力とは、常に自分を叱咤することではなく、音楽に素直でいようとすること――。
再びノートを開く ― 変化した「書き方」
しばらくして、私は再びノートを開きました。でも、以前のように「ミスの分析」ではなく、「心の記録」を書くようにしました。
たとえばこんなふうに。
- 本番前、ホールの響きが温かく感じられた
- 弓を引いた瞬間、客席の空気が変わった気がした
- 2楽章の入りで、ピアノと心が重なった
分析ではなく、感覚をそのまま記す。良し悪しを判断せず、「感じたこと」を残すだけ。
すると、書くこと自体がまた“音楽の一部”のように感じられるようになりました。それは、心と技術を切り離さずに育てるための、小さな習慣になっていったのです。
スランプは「敵」ではない
スランプの時期というのは、往々にして「停滞」ではなく「変化の予兆」です。自分が次の段階に進もうとしているからこそ、今までのやり方が通じなくなる。つまり、スランプとは「成長の入り口」なのです。
私の場合、分析に頼りすぎていた心が、「感じる」力を取り戻すことで、音楽の本質にもう一度触れることができました。
そして今、あの苦しかった時期を振り返ると、あのスランプがなければ、私は今の音を奏でることはできなかったと思います。
おわりに ― 「やめる」こともまた、勇気
音楽の世界では、「続けること」や「努力し続けること」が称えられます。けれど、時には「やめること」も大切な選択です。分析をやめる。練習をやめる。完璧を目指すのをやめる。
それは怠けではなく、「新しい自分を受け入れるための静かな勇気」です。
私がスランプを抜け出せたのは、分析ノートを閉じ、心の声に耳を傾けたその瞬間でした。
音楽は、理屈ではなく“感情の呼吸”でできています。その呼吸を取り戻したとき、初めて「自分の音」が聴こえてくる。
そして今日も私は、「感じる」ことを大切にしながら、少しずつ新しい音を探し続けています。
まとめ ― スランプに悩む人へ
もし今、あなたがスランプの中にいるなら、どうか焦らず、自分を責めないでください。
- 分析を少し手放してみる
- 「できた/できなかった」ではなく「感じたこと」を書く
- 音の美しさを、もう一度“好き”になる
それだけで、きっと音楽はまたあなたの味方になってくれます。
努力の先にあるのは「正解」ではなく、「あなた自身の音」。どうか、その音を信じてください。
スランプは、音楽を志すすべての人に訪れる通過点。分析も大切ですが、ときには「心で聴く」時間が必要です。音楽があなたの中にもう一度“息を吹き返す瞬間”が訪れますように。