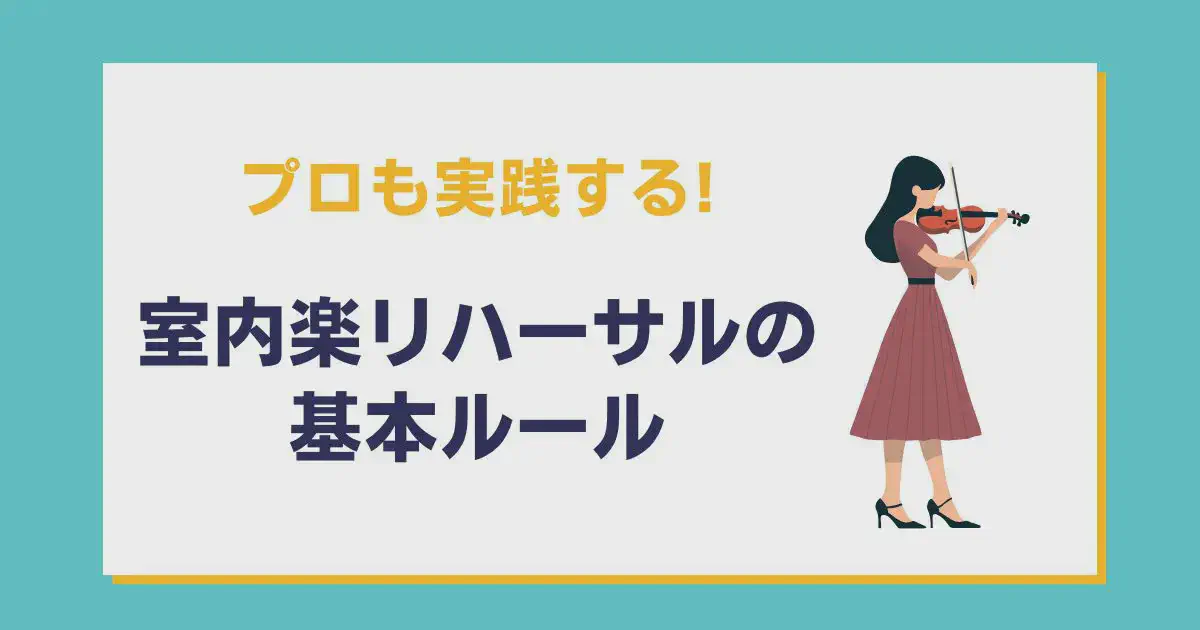弦楽器の室内楽は、個々の高度な演奏技術に加え、対話的なアンサンブル能力が不可欠なジャンルです。リハーサルでは単なる音合わせに留まらず、音楽的な解釈、フレージング、響きの構築まで、細やかな調整を重ねていく必要があります。
ここでは、室内楽リハーサルをより実りあるものにするために意識したい6つのポイントを挙げます。
1. リスニングの質を高める
室内楽において「聴く」という行為は受動的なものではなく、能動的な音のキャッチと反応が必要です。特に意識すべきは以下の3点です。
- 主旋律、対旋律、内声、それぞれの役割を聴き分ける
- 和声進行に応じて響きのバランスをリアルタイムで調整する
- 他パートのアーティキュレーションや音色に合わせて瞬時に自分の奏法を変化させる
自分が演奏していない間も、常に音楽の中に「参加」している意識を持つことが重要です。
2. リハーサル前のスコアリーディング
リハーサル前にパート譜だけでなくスコアに目を通しておきましょう。
各パートの動き、和声進行、曲の構造を把握しておくことで、単なる自分のパート演奏から脱し、アンサンブル全体を俯瞰する感覚を養えます。
また、重要なモティーフの受け渡し、ハーモニーの変化点などをあらかじめ意識しておくことで、リハーサル中のディスカッションも格段に深まります。
3. 発音のタイミングとアタックを合わせる
弦楽器の室内楽では、音の立ち上がりの統一が極めて重要です。ボウイングの開始位置、スピード、圧力を合わせることで、フレーズのまとまりが生まれます。
- ボウイングを共有する
- 目線を合わせたり、呼吸を合わせて同時に「入り」を作る
この「瞬間の一致」が生まれると、アンサンブルはぐっと引き締まります。
4. 音程
弦楽器同士のアンサンブルでは、ピタゴラス音律や純正律に基づいて音程をとる必要があります。
- 根音と第5音の5度をまずは合わせる
- 5度があったら、5度の響きにあう音程で第3音を弾く
- 長三和音の場合は第3音は少し低め、短三和音の場合は第3音は少し高めにとります
単にチューナーに合った音を出すのではなく、場面ごとに適切な音程を作り上げ、響きの純度を高めることが求められます。
5. フレージングとアーティキュレーションの統一
同じフレーズを弾く際、ボウイング、ヴィブラート、ダイナミクスの設計を揃えることも不可欠です。
- フレーズの起承転結を共有する (どこに向かい、どこで収めるか)
- デタッシェ、レガート、スピッカート等、アーティキュレーションを一致させる
特に、音楽的な「語尾」 (終わり方) を揃えると、全体の完成度が一段と上がります。
6. 柔軟なリハーサル進行と試行錯誤を恐れない
リハーサルでは一つのやり方に固執せず、いくつかのアプローチを試してみることが大切です。
- テンポ設定を数パターン試す
- ボウイングを変えてみる
始めから「合わせよう」とするのではなく、一緒に試行錯誤を重ねることで自然と「寄ってくる」のです。
まとめ
弦楽器の室内楽リハーサルは、技術、耳、感性、そしてコミュニケーション能力すべてを総動員する濃密な時間です。
単なる「合わせ」ではなく、作品への深い理解と、お互いの表現への尊重をベースに進めることで、自分一人では得られない体験ができるでしょう。
アカデミーカスタマイズでは室内楽レッスンを実施しています。
詳しくはこちらをご覧ください。