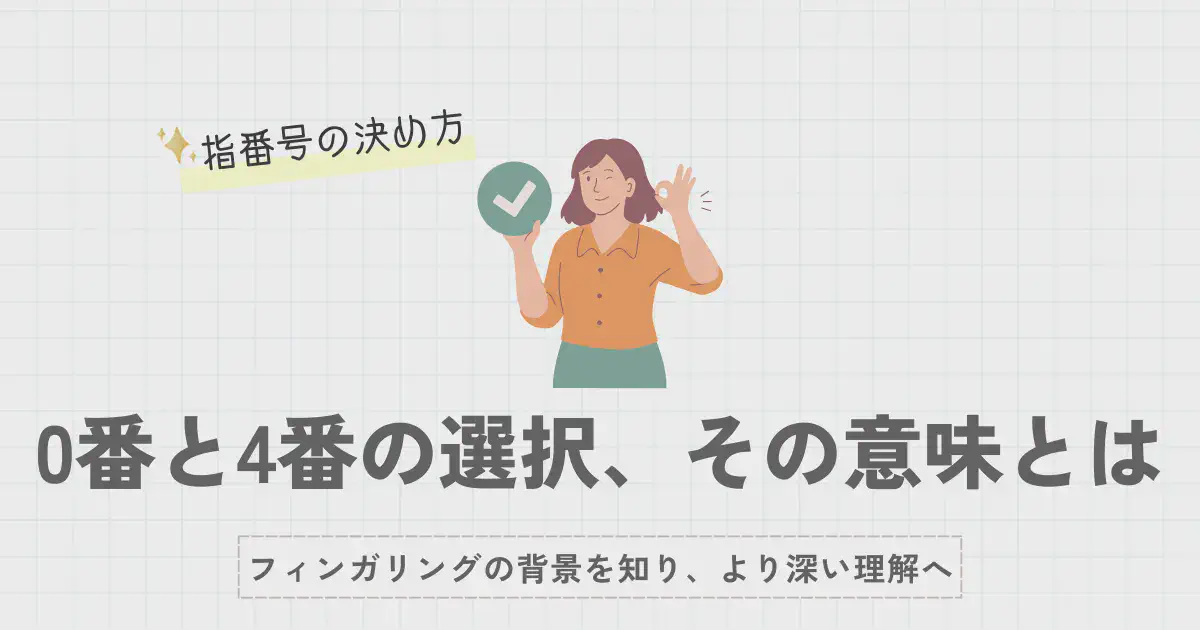〜フィンガリングの背景を知り、より深い理解へ〜
突然ですが質問です。
ヴァイオリンには、0番 (開放弦) でも4番 (小指) でも弾ける音があります。例えば以下の音。
- G線のレ
- D線のラ
- A線のミ
いずれも1stポジションで、0番の開放弦と4番の指で同じ音が出せます。
「そんなの初歩的なことじゃない!」と思った方もいるかもしれません。でも、ここで一度立ち止まって、この“選択”について少し深掘りしてみませんか?実はこの0番と4番の選択には、ヴァイオリン演奏の歴史や技術的な背景が密接に関係しているのです。
今日は、教本や名著を参考にしながら、「なぜ0番?なぜ4番?」というシンプルだけど奥の深いテーマについて考えてみたいと思います。
1. 小野アンナの音階教本: 基礎の基礎にあるルール
まず最初に取り上げたいのは、ヴァイオリンを学ぶ人なら誰しもが一度は目にしたことのある「小野アンナの音階教本」です。
この教本では、上りの音階では開放弦 (0番) を使い、下りの音階では4番の小指を使うという形が基本になっています。例えば、D線のラを上るときは0番のA線を使い、下るときはD線の4番で弾く、というように。
この理由にはいくつかの要素がありますが、主に以下の点が挙げられます:
- 開放弦の響きを活かして音階の流れに明るさを加える
- 下りでは滑らかさと安定感を出すために同じ弦上で完結させる
初心者にとっては、弦の移動を最小限にしながら、フィンガリングの感覚を養うという意味でも、理にかなった方法です。
2. カール・フレッシュ: 指づかいの思想が反映された音階
次に紹介するのは、より専門的かつ高等教育の現場でも使われる「カール・フレッシュの音階教本」です。
驚くことに、こちらは上りが4番、下りが開放弦という構成になっています。小野アンナとは真逆のアプローチです。
なぜこのような違いがあるのでしょうか?
その鍵は、演奏技術と音楽的表現のバランスをどこに置くかという思想にあります。
- 上行時に4番を使うことで、音階全体を滑らかに、そして均一な音色で弾くことができる
- 下行時に開放弦を使えば、響きを自然に消していくことができる (減衰効果)
フレッシュの意図は、単なる指の運動ではなく、音の流れや質感にまで目を向けることにあったのです。
3. ヴァイオリニストのバイブル: 「演奏の技法」という知の結晶
「カール・フレッシュ著 ヴァイオリン演奏の技法」は、現在は絶版になっている貴重な文献ですが、その内容はまさに“演奏のバイブル”と呼べるものです。
この本では、単なるテクニック論にとどまらず、
- 練習時間の構成方法
- 音階やアルペジオの意味づけ
- 演奏におけるメンタルコントロール
など、ヴァイオリニストとして生きるためのあらゆる知恵が詰まっています。
たとえば、「たった1音のために弦を変えるか否か」という判断基準ひとつにも、明確な理論と目的があることが説明されています。
ここで重要なのは、「慣れているから」「楽だから」という選択ではなく、音楽的に意味のある選択をしようということなのです。
4. 技術の進化とともに変わるフィンガリングの常識
フレッシュが述べている中で特に興味深いのは、弦素材の変化がフィンガリングの考え方を変えたという点です。
昔はガット弦が主流で、開放弦は明るく自然な響きを持っていたため、積極的に使用されていました。しかし、スチール弦 (特にE線) の登場によって、状況は一変します。
スチール弦の特徴は、
- 明確で鋭い音が出る反面、
- スラーの中で開放弦に移ると音が“浮きやすい”
という弱点があります。これにより、スラー中での移弦や音色の統一を保つために、4番を選ぶ場面が増えてきたのです。
技術が進歩することで、フィンガリングの常識も進化していく。これもまた、ヴァイオリンという楽器の奥深さと言えるでしょう。
5. 実際の演奏での選択: どうやって決める?
実際に曲を弾く際、「開放弦を使うべきか、4番を使うべきか」で悩んだことはありませんか? たとえば:
- バッハの無伴奏で開放弦の“鳴り”を活かすか
- ロマン派の作品で音色を統一するために4番を使うか
- 移弦を避けて流れを重視するか
こうした判断は、単なる技術の問題ではなく、音楽の意図と調和している必要があります。また、ホールの響き方や伴奏とのバランス、録音環境なども関係してくるでしょう。
6. まとめ: 自分の中に“選択の軸”を持つこと
今日お話した通り、0番と4番の選択には歴史的背景、演奏思想、使用弦の素材、そして音楽的文脈など、さまざまな要因が影響しています。
どちらが正しい、という単純な話ではありません。むしろ大切なのは、なぜその指を使うのか、自分で説明できる理由を持つこと。
選択には意図があり、意図には音楽が宿ります。
自分の癖や好みだけに頼るのではなく、その場その場で最適な選択ができるようになるためにも、ぜひ今日の話を演奏に活かしていただけたら嬉しいです。
おまけ: こんな練習もおすすめです!
最後に、指遣いの感覚を広げる練習として、こんなことを試してみてはいかがでしょうか?
- 音階練習を「全部0番あり」「全部4番で」の2パターンで弾いてみる
- 弾いたときの音色の違いを録音して比較する
- スラーとスタッカートでの使いやすさをそれぞれ確認する
実際に試してみると、「この指の方がラク」だけでなく「こっちの方が美しい」「音楽が自然に流れる」といった感覚が見えてくるはずです。
音階練習は単調に感じがちですが、実はとてもクリエイティブな作業。今日からまた、新しい目で取り組んでみてくださいね。